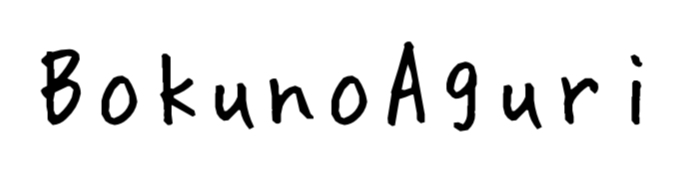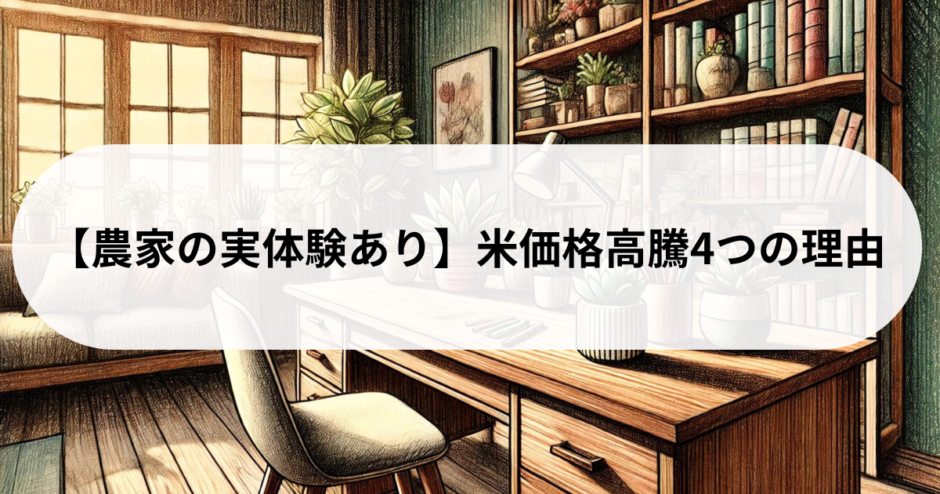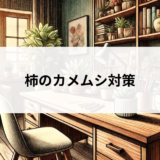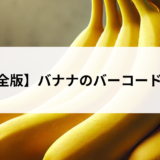この記事では、次の疑問が解決できます。
- なぜいま米の価格が上がっているの?
- 農家はその影響をどう感じている?
- 今後の米価はどうなっていくの?
本記事では、米価高騰の主な原因について、農家目線で何が起きているか、実体験を交えながら考え記事にしてみます。
1. 飲食店の需要増加|外国人観光客の影響
ここ2・3年、飲食店から農家へのお問い合わせが増えています。
通常、米は卸業者を介して仕入れるのが一般的ですが、飲食店が農家と直接取引を行うケースが急増しています。
確かに、まわりの米農家に聞いても、「電話きた」と言っています。
なぜ?
と思ったので、知り合いの飲食店に聞いてみました!
その結果、外国人観光客の増加による和食需要の高まりが関係していました。
観光庁が公表しているデータで、調べてみるとよくわかります。
2024年の訪日外国人は3687万人で、2019年の3188万人を上回り過去最多を記録。
前年比1104万人(+42.7%)増と大幅増加し、新型コロナの影響で落ち込んだ2020〜2021年から完全回復していました!
| 年 | 訪日外国人旅行者数(万人) |
|---|---|
| 2019 | 3188 |
| 2020 | 411 |
| 2021 | 24 |
| 2022 | 383 |
| 2023 | 2500 |
| 2024 | 3687 |
より詳細なデータは 観光庁の公式ページ で確認できます。
2. 米の生産量が減少|過去15年で21%減少!
米価高騰のもう一つの要因が、生産量の減少です。
日本の米生産量は長期的に減少傾向にあり、2024年には過去15年で約34万トン減少しました。
私の周りの農家も減り、若手農家や法人が使われなくなった土地を活用して耕作面積を増やしているが、それでも生産量は減少している状況です。
農林水産省が公表しているデータをみても、H20年の生産量からグンと減っています。
| 年度 | 生産量(万トン) | 減少量(万トン)H20から |
|---|---|---|
| 2008(H20) | 159 | 0 |
| 2018(H30) | 138 | -21 |
| 2024(R6) | 125 | -34 |
3. 生産コストの上昇|肥料・燃料の高騰が影響
農家が米を生産するためのコストも大幅に上昇しています。
特に、肥料・燃料・電気代の高騰が顕著です。
主要コストの上昇率(前年比)
| 項目 | 2023年 | 2024年 | 上昇率 |
|---|---|---|---|
| 肥料価格 | 100 | 130 | +30% |
| 農薬価格 | 100 | 120 | +20% |
| 軽油価格(円/L) | 90 | 140 | +55% |
| 電気代(指数) | 100 | 135 | +35% |
我が家もそうですが、周りの農家の声を聞いても、「販売価格は上がっているが、手取りは増えていない」という意見が多く、生産コストの上昇が利益を圧迫しているのが現状です。
特に、イチゴやトマト等のハウス栽培農家はは、「光熱費の高騰がバカにならない!」とよく言っています。
4. 市場への流通減少 直接販売と契約販売が影響?
市場への米の流通量が減少している理由は次の①直接販売の増加、②備蓄米の放出抑制、③契約販売の拡大が挙げられます。
① 直接販売の増加
飲食店や個人消費者が農家から直接購入するケースが増えています。
- 卸価格の高騰 → 直接購入の方が安い
- 品質重視の飲食店が農家と直接取引
- 市場経由の流通量が減少(前年比 約-12%)
② 備蓄米の放出抑制
政府が備蓄米の管理方針を変更し、市場への供給量を抑制しています。
- 2024年の市場放出量:前年比 約-10%
- 市場価格維持のため、供給量を調整
③ 契約販売の拡大
市場での競り取引が減少し、大手業者との契約販売が主流に。
- 市場競争力の低下 → 価格形成が難化
- 契約価格が固定化 → 柔軟性が失われる
- 市場の人手不足も影響
5. まとめ|今後の米価の動向に注目!
最後にまとめです。
米価高騰の主な要因
長期的な生産量の減少(過去15年で-21%)
高温障害や害虫被害による収量減少
燃料・肥料価格の高騰(前年比+20%〜30%)
契約販売の増加による市場価格の変動
米価の高騰は、単なる一時的な問題ではなく、複数の要因が絡み合った結果です。
個人的見解ですが、今後の動向を整理してみます。
- 2025年も米価は上昇する可能性あり(少なからず下がることはない)
- 生産コスト削減の方法を模索(原料高騰)
- 市場流通の健全化